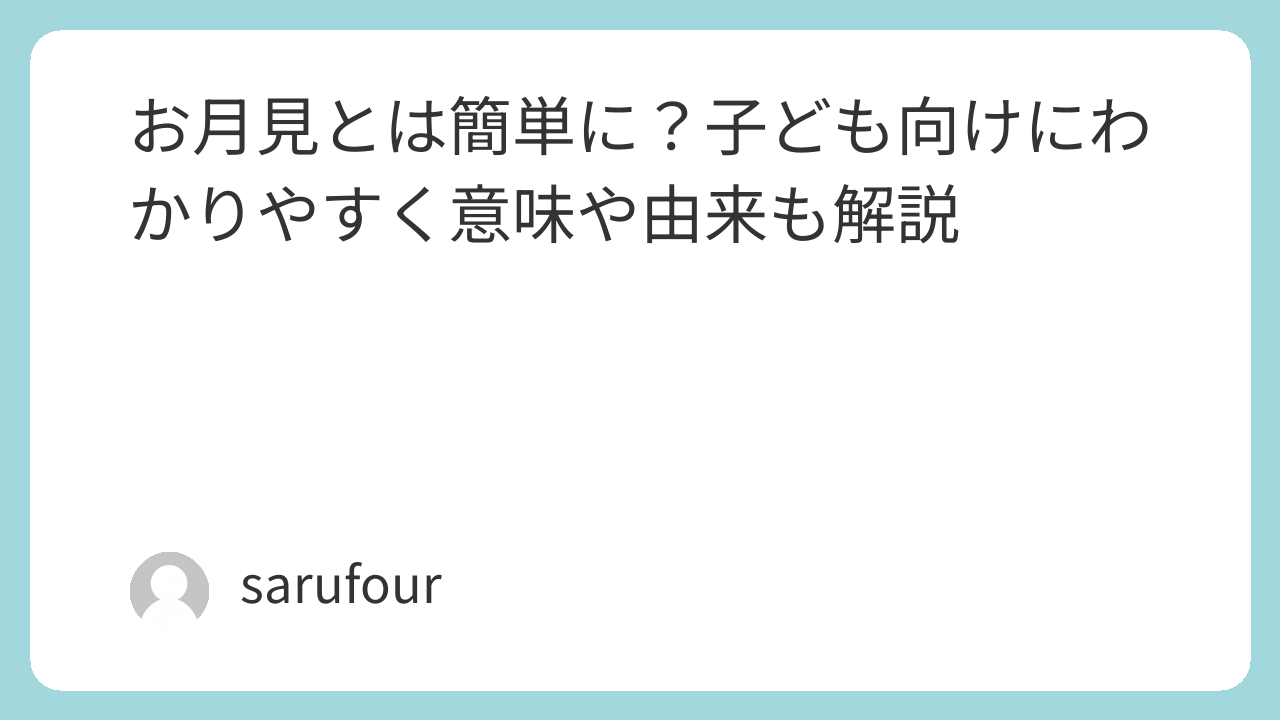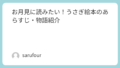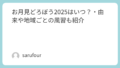子どもにもわかりやすく簡単に言うと、お月見とは「ありがとう」「豊作でうれしいね」という気持ちを月に伝える日です。
お月見とはどんなことをする行事なのかをわかりやすく解説します。
お月見の歴史や、団子・すすきなどの飾りの理由、当日の過ごし方までを簡潔にまとめているので、
「お月見とは簡単に説明するとどういう意味?」という子どもからの質問にもそのまま答えられます。
この記事を読めば、お月見の由来や食べ物の意味まで自然に理解できるようになります。
お月見とは何?子どもにもわかる簡単な意味と由来
お月見とは、秋のきれいな月をながめながら、自然に感謝する行事のことです。
「十五夜(じゅうごや)」とよばれる満月の日に、
家族や友だちと月を見て、団子などをお供えします。
日本では昔から、月は神さまのいる特別なものと考えられてきました。
お月見の由来は平安時代とされており、
中国から伝わった「月を愛でる文化」が日本の風習と合わさって広まったといわれています。
子どもにもわかりやすく言うと、
「ありがとう」「豊作でうれしいね」という気持ちを月に伝える日です。
お月見には何をするの?お供えや行事の内容を簡単に紹介
お月見の日には、次のようなことを行います。
月をながめる
夕方から夜にかけて、丸くて明るい満月をゆっくり見ます。
これを「月を愛でる(めでる)」といいます。
家の窓から見るだけでも、お月見気分を味わえます。
お供えをする
お月さまに感謝を伝えるために、団子や野菜・すすきなどをお供えします。
団子は月の形に似ているため、縁起がよいといわれています。
また、すすきは稲の代わりとして飾られ、豊作を願う気持ちが込められています。
秋の味覚を楽しむ
お月見の時期は、さつまいもや栗など、秋の食べ物がおいしい季節です。
そうした食べ物を囲んで、家族で過ごすのもお月見の楽しみのひとつです。
お月見の食べ物や飾りは?団子・すすきの理由も簡単に解説
お月見団子
お月見といえば、まっ白くて丸いお月見団子。
これは満月をかたどった形で、感謝や願いを込めてお供えします。
団子の数は地域によって違い、関東では15個、関西では12個が一般的です。
お団子はお供えしたあとに食べてもよく、「月の力をいただく」と考えられています。

すすき
すすきは、稲のように穂がついているため、
五穀豊穣(ごこくほうじょう)を願う意味で飾られます。
また、すすきの葉には邪気をはらう力があると信じられてきました。
子どもと一緒に野原で摘んでくるのも、お月見の思い出になります。
その他の食べ物
さつまいも・栗・ぶどう・梨など、秋にとれる季節の果物や野菜もおすすめです。
これらも感謝の気持ちをこめて、お月さまにお供えしましょう。
お月見とは簡単に?子ども向けに意味や由来を伝えるまとめ
お月見は、きれいな月を見ながら、自然の恵みに感謝する行事です。
月に向かって「ありがとう」と言ったり、団子やすすきをお供えしたりすることで、
日本の伝統行事に親しむことができます。
難しいことを教えなくても、
「今日は特別な満月を楽しむ日なんだよ」と伝えるだけで十分です。
子どもと一緒に団子を作ったり、絵本を読んだり、お月さまを見上げたりして、
心に残るお月見の時間を過ごしてみてくださいね。