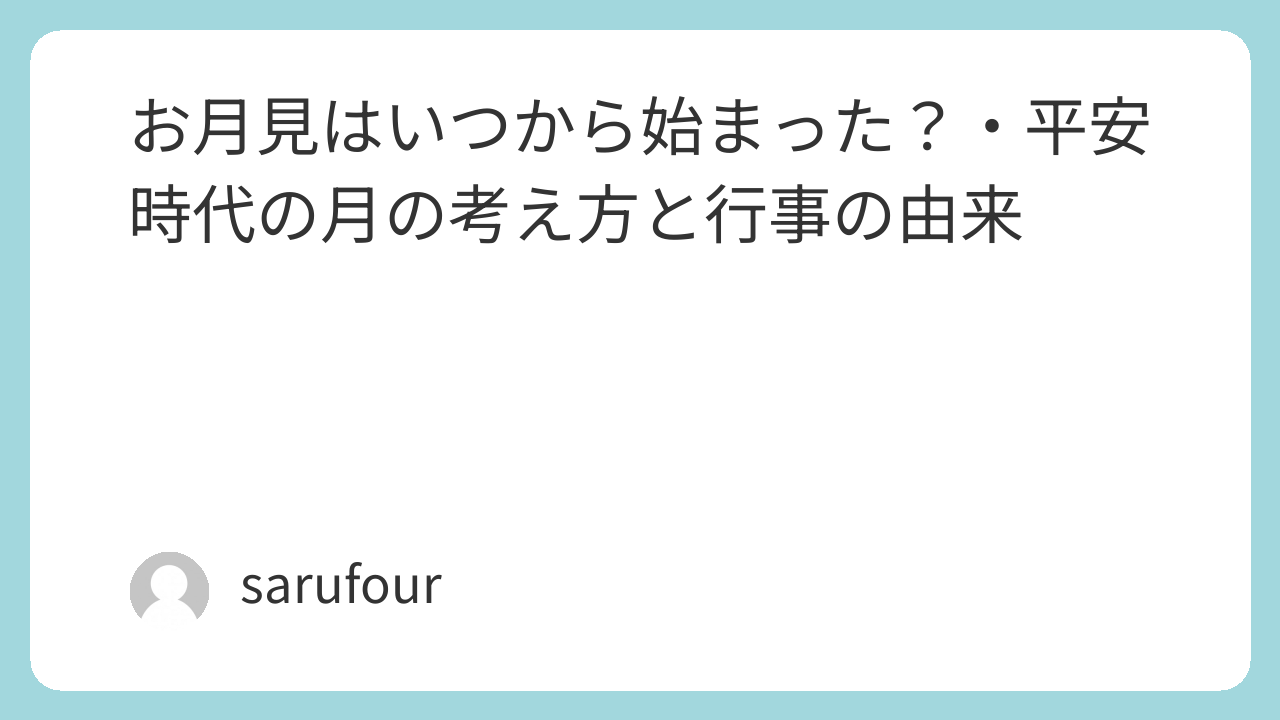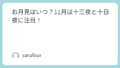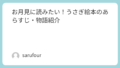お月見はいつから始まった?その答えは平安時代にあります。
お月見の始まりは、中国の中秋節がルーツとなり、平安時代に日本独自の行事として定着したのが始まりです。
現在のように十五夜に月を眺める風習は、平安時代の貴族が月を愛でながら詩歌を詠む「観月の宴」を楽しんだことに由来しています。
この記事では、
- お月見が始まった背景(由来・起源)
- 平安時代の人々の月に対する考え方や文化
- 現代まで続くお月見の楽しみ方や食べ物
などを日本文化の視点からわかりやすく解説しています。
お月見はいつから始まった?平安時代の由来と行事の始まり
お月見が日本で始まったのは、平安時代とされています。
中国から伝わった中秋節(ちゅうしゅうせつ)の風習がもとになり、貴族たちの間で月を愛でる行事として定着しました。
特に十五夜には、舟に乗って水面に映る月を眺めながら詩を詠む「観月の宴(かんげつのうたげ)」が行われていた記録があります。
このような風流な月見文化が、次第に庶民にも広がり、お月見=秋の風物詩として根づいていきました。
十五夜のお月見は、毎年旧暦8月15日(新暦では9月〜10月)に行われ、2025年は10月6日(月)がその日にあたります。
平安時代の月の考え方と日本文化としてのお月見
平安時代の人々にとって、月は美しさ・神秘・季節の象徴でした。
特に満月は、「完全」や「調和」を意味し、精神的な安らぎを与える存在としても大切にされていました。
また、当時の和歌や物語にも「月」が頻繁に登場し、心の機微や自然とのつながりを表現する象徴として用いられていたのが特徴です。
お月見はただ月を眺めるだけでなく、自然と心を通わせる文化的な営みだったのです。
このような月への思いは、日本文化の美意識にも深く影響を与え、現代でも中秋の名月や俳句などにその精神が受け継がれています。
お月見には何をする?食べ物や行事内容を紹介
お月見では、月を眺める(観月)だけでなく、季節の収穫に感謝する意味合いも込められています。
代表的な行事内容には、以下のようなものがあります。
お供え物の定番:月見団子
月見団子は、十五夜に供える丸いお団子で、満月を模した形が特徴です。
白くて丸い形は、豊作・健康・幸福を祈る象徴とされており、地域によっては芋を供える「芋名月」とも呼ばれています。
🎁 お月見の定番「月見団子」は通販でも手に入ります!
▼楽天で人気の月見団子セットはこちら
楽天市場で月見団子を探す ▶
季節の野菜やすすき
月見団子と一緒に供えるのが、里芋や栗、枝豆などの収穫物です。
また、すすきは稲穂の代わりとして飾られ、魔除けや豊作祈願の意味があります。
🌾 飾るだけでお月見ムードがアップ!
▼楽天で人気のお月見用すすき・飾りはこちら
楽天市場ですすき飾りをチェック ▶
家族で楽しむお月見
最近では、家庭でもベランダや縁側などでお月見を楽しむ人が増えています。
子どもと団子を手作りしたり、月の観察を楽しんだりするなど、現代風のお月見の楽しみ方も広がっています。
お月見の始まりと平安時代の文化まとめ
お月見は、平安時代の貴族文化から始まった日本の伝統行事です。
中国の風習が日本流に変化し、観月・収穫祭・感謝の行事として現代に受け継がれています。
月は古くから美しさと調和の象徴として愛され、お月見は月とともに心を整える大切な行事でもありました。
月の美しさと季節の恵みに感謝しながら、日本文化の豊かさを感じるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。