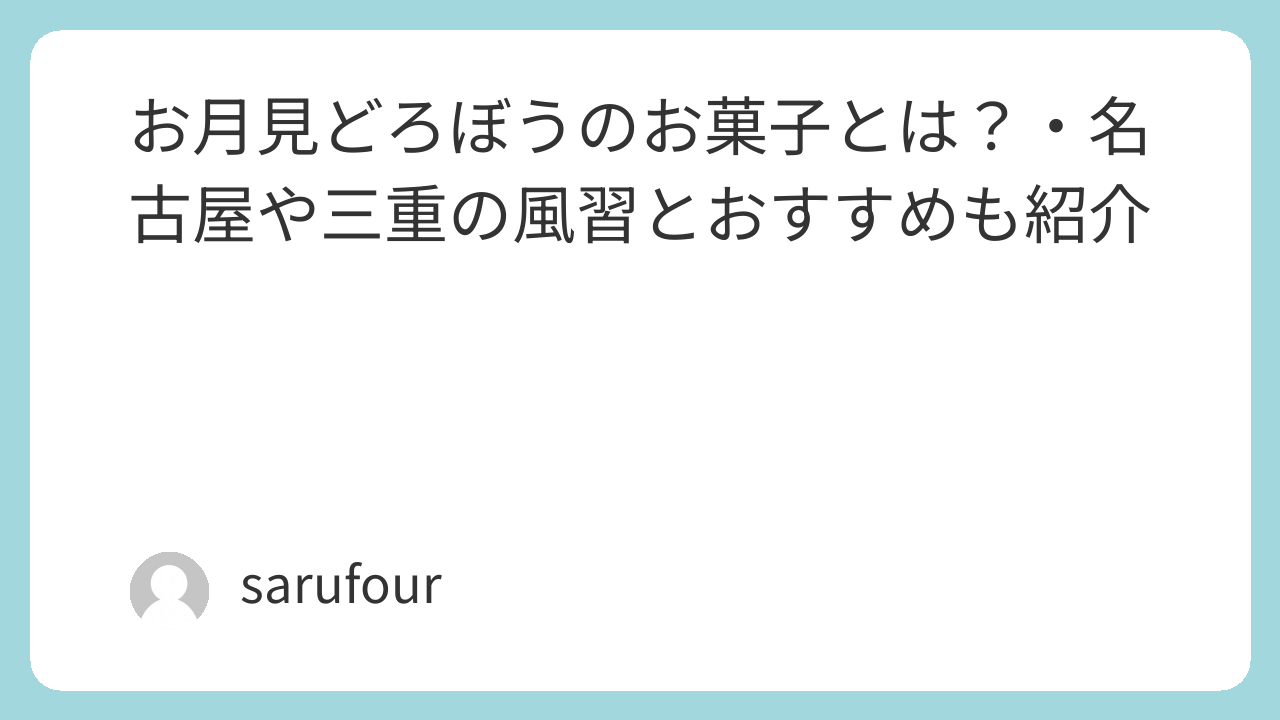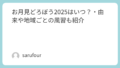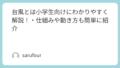お月見どろぼうで配るお菓子は、気軽に取れて安全な個包装が基本です。
駄菓子やゼリー、季節感のあるうさぎモチーフのお菓子が定番となっています。
この記事では、お月見どろぼうの意味や由来に加え、配るお菓子のおすすめや地域ごとの違い、基本的なルールもわかりやすく解説しています。
お月見どろぼうのお菓子とは?配る理由やルールも解説
お月見どろぼうとは、十五夜に子どもたちが地域の家を回ってお菓子をもらう行事です。
ハロウィンに似ていますが、由来は日本の伝統行事である月見と収穫感謝にあります。
配るお菓子は、地域によって違いがありますが、個包装の駄菓子やゼリー、おせんべいなどが定番です。
あらかじめ家の前に「お月見どろぼうOK」などの札を掲げる家庭もあり、子どもも安心して楽しめるよう地域全体で工夫されています。
基本ルールとしては、
- 十五夜の夕方〜夜に実施
- 玄関先のお菓子だけを取る
- 家にはインターホンを鳴らさず静かにまわる
というのが一般的です。
名古屋や三重の風習とは?お月見どろぼうの地域ごとの特徴
お月見どろぼうは、愛知県・名古屋市や三重県などの一部地域で古くから続く風習です。
名古屋市・日進市など愛知県の例
名古屋市や日進市では、地域の自治会や子ども会が主催することもあり、
「お月見どろぼう袋」や「どろぼうカード」を配布するところもあります。
一部の小学校では地域学習として取り上げられるほど定着した文化となっています
三重県・鈴鹿市の例
三重県では、「おつきみどろぼう」と呼ぶ地域もあり、
子どもたちが静かにお菓子を集めて歩く光景が見られます。
近年は、防犯上の理由から開催地域が限定されつつある一方で、
地域活性化の一環として改めて注目されるケースも増えています。
お月見どろぼうのお菓子選び方は?配るのにおすすめの商品も紹介
お月見どろぼう用のお菓子は、手に取りやすく衛生的で、誰にでも喜ばれるものが最適です。
おすすめは以下の通りです。
定番:個包装の駄菓子詰め合わせ
お月見どろぼうといえば、たくさんの子どもがまわることが前提なので、
コスパがよくて数が多い駄菓子セットが定番です。
季節感あるお菓子
月見団子風の和菓子、うさぎモチーフのお菓子なども人気です。
季節限定パッケージを選べば、見た目にも楽しめる特別感が演出できます。
アレルギーや年齢配慮も忘れずに
乳・卵・小麦を避けた配慮のあるお菓子も入れると、より多くの子どもが楽しめます。
対象年齢が低い地域では、ゼリーやラムネなど食べやすいものがよいでしょう。
お月見どろぼうのお菓子まとめ・地域交流としての魅力とは
お月見どろぼうのお菓子は、単なるおやつではなく、地域交流を生む“きっかけ”です。
・子どもたちはお月見の意味を知るきっかけになる
・地域の人たちは互いの顔を知ることで防犯にもなる
・日本の文化を受け継ぐ行事としても価値が高い
というように、「お菓子を配る」だけでなく、つながりを生む文化的な行為です。
近年はイベントとしての色が強まっていますが、
昔ながらの意味やルールを知ったうえで参加することが大切です。
2025年の十五夜は10月6日(月)。
今年はぜひ、お菓子を通じた優しいつながりを楽しんでみてください。