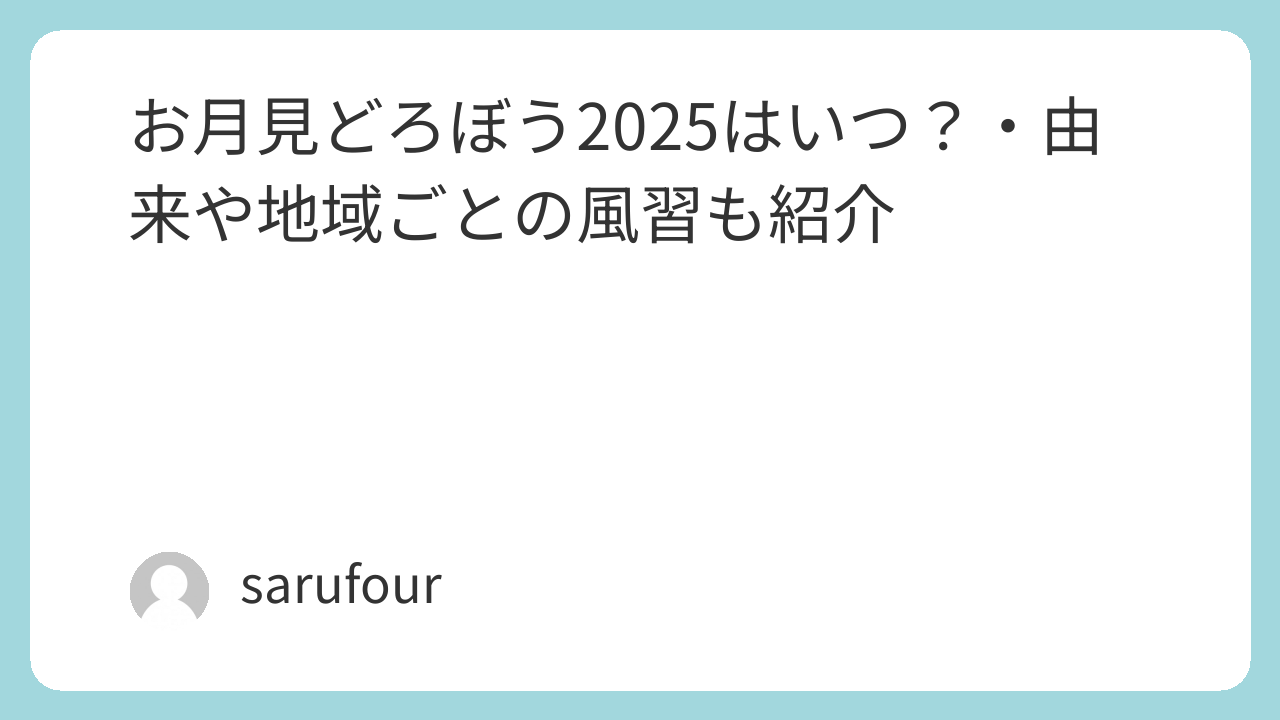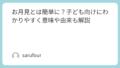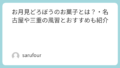お月見どろぼうとは、十五夜に子どもたちが地域の家々を回ってお菓子をもらう、日本版ハロウィンのような行事です。
2025年のお月見どろぼう(十五夜)は10月6日(月)ですが、満月は翌日の7日(火)です。
東海地方などを中心に今も残る風習で、もともとは月への感謝や豊作祈願に由来する縁起行事でした。
この記事では、お月見どろぼうの意味・由来・地域ごとの違い・2025年の日程やルールをわかりやすく解説。
お月見どろぼう2025年はいつ?日にちと基本ルールを紹介
お月見どろぼうは、十五夜(中秋の名月)の日に行われる地域行事です。
十五夜(中秋の名月)にあたる2025年の開催日は、10月6日(月)です。
この日、子どもたちが近所の家を回ってお菓子をもらうのが「お月見どろぼう」の基本的なスタイルです。
見た目はハロウィンのようでも、由来は日本古来の月見文化や収穫への感謝の気持ちに根ざしています。
あらかじめ玄関先にお菓子を用意しておく家庭もあり、地域ぐるみの温かな風習として続いています。
🌕【お月見どろぼう用におすすめ!】小分けで配りやすいお菓子を楽天で探す>>>
お月見どろぼうの由来とは?昔話や絵本でも語り継がれる風習
お月見どろぼうの始まりは明確ではありませんが、江戸時代ごろから見られたと考えられています。
秋の収穫を祝う「十五夜」に、子どもが供え物をそっと持ち帰ると福が訪れるとされたことが名前の由来です。
これは「盗む」という意味ではなく、“福を持ち帰る”縁起の良い行動として受け入れられてきました。
その風習を元にした絵本『おつきみどろぼう』があります。
子ども向けに伝統行事をやさしく紹介する教材としても使われています。
日本文化としての背景には、月に宿る神様への感謝や祈りという意味合いもあり、
ただのお菓子イベントではない“深み”がある行事です。
地域によって違う?お月見どろぼうの実施状況と現代の取り組み
お月見どろぼうは、東海地方(愛知県・三重県・岐阜県)の一部や、福島県・静岡県・宮崎県など、限られた地域で行われています。
愛知県日進市や名古屋市、三重県四日市市、岐阜県恵那市、福島県東白川郡など限られた地域で今も行われており、地元の子ども会やPTA、商店街が協力して開催するケースも多く見られます。
最近では防犯やトラブル防止の観点から、事前に名簿やルートを決めて回る地域も増えました。
また、「お菓子を配る家」にはお月見どろぼうOKの札を掲げるなど、
地域全体で安全・安心に楽しめる工夫も広がっています。
一方で、風習が廃れつつある地域もあり、SNSなどを通じた啓発活動も行われるようになりました。
お月見どろぼう2025まとめ・風習の魅力と日本文化としての価値
お月見どろぼうは、十五夜に子どもが“福を分けてもらう”日本の伝統行事です。
2025年は10月6日(月)(ただし満月は翌7日)がその日にあたります。
子どもたちの笑顔や地域のつながりを育む行事として、
今も各地で独自のスタイルで受け継がれています。
昔ながらの「感謝の心」と「地域交流」を残したい方には、
お月見どろぼうの風習を知る・伝えることが一つのきっかけになるかもしれません。
今年の十五夜は、秋の夜空を見上げながら、日本文化の温かさを感じてみてはいかがでしょうか。
関連記事
お月見の行事自体の始まり(由来)についてはこちら。
お月見について子どもにも簡単にわかる解説はこちら。