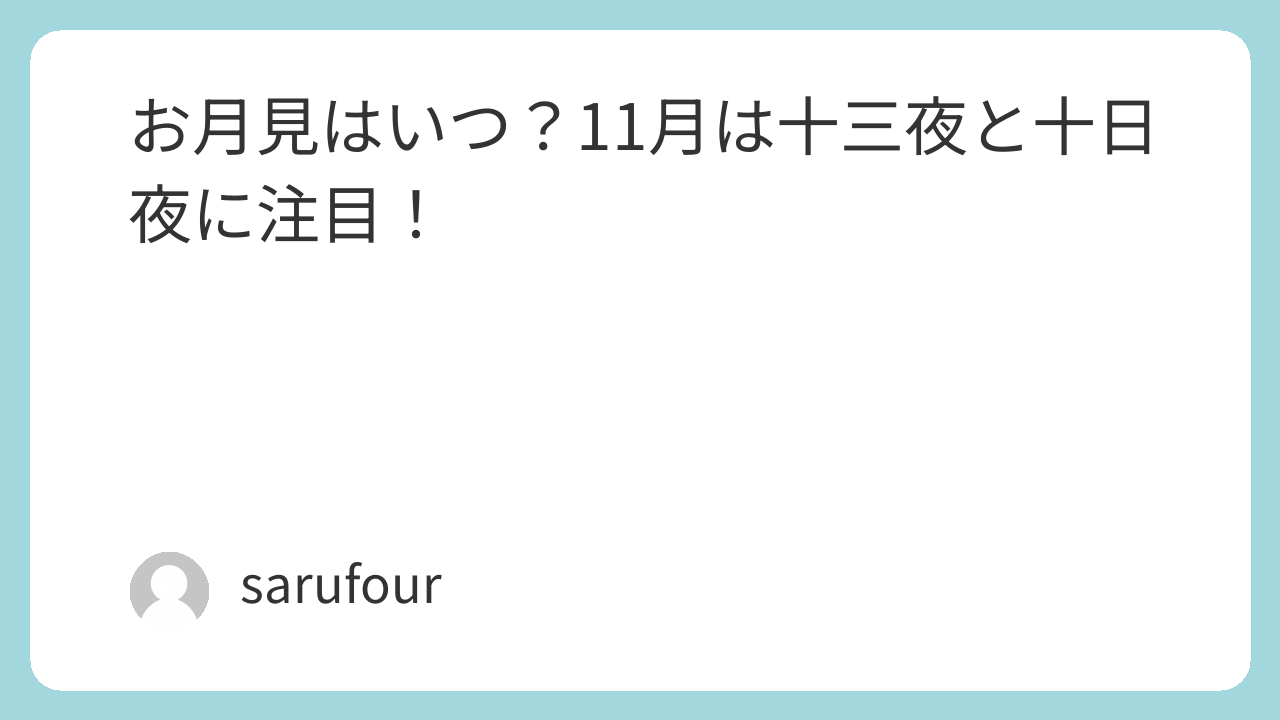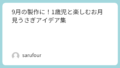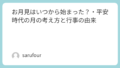結論から言うと、2025年のお月見行事は以下の通りです。
- 十三夜(じゅうさんや)…11月2日(日)
- 十日夜(とおかんや)…11月29日(土)
どちらも十五夜(中秋の名月)とは別の日に行われる、
伝統的な秋の月見行事です。
十五夜だけでは片月見とされ縁起が悪いとも言われており、
十三夜まで楽しむのが昔ながらの過ごし方とされています。
※十三夜と十日夜は旧暦で決まるため、毎年の日付は変動します。この記事では意味や違いが分かるようにまとめているので、毎年の月見の参考にも使えます。
この記事では、
- 2025年の十三夜・十日夜の意味と日程
- 9月・10月のお月見との違い
- お月見で何をするのか?食べ物や飾りの意味も紹介
などをわかりやすくまとめています。
お月見はいつ?11月の十三夜・十日夜の日程と意味とは?
「お月見=9月や10月」と思っている方も多いかもしれません。
でも実は、11月にもお月見行事があります。
その代表が「十三夜(じゅうさんや)」と「十日夜(とおかんや)」です。
十三夜は、中秋の名月(十五夜)から約1か月後に行うお月見で、
旧暦9月13日の夜にあたります。
2025年の十三夜は11月2日(日)です。
十五夜だけ祝うのは「片月見(かたつきみ)」とされ、
縁起が悪いとも言われるため、両方見るのが吉とされます。
一方、「十日夜」は旧暦10月10日の行事で、
2025年は11月29日(土)にあたります。
十日夜はお月見というよりも収穫祭の意味合いが強く、
東日本を中心に行われている伝統行事です。
お月見は何月にするの?9月・10月・11月の違いを解説
お月見といえば、最も有名なのが「十五夜(中秋の名月)」です。
これは旧暦8月15日の夜に見える満月を愛でる風習で、
現代の暦では9月中旬から10月上旬にあたります。
つまり、多くの人がイメージする「お月見」は9月〜10月頃です。
そして、そこから約1か月後の旧暦9月13日=十三夜は、
毎年10月中旬〜11月上旬ごろに行われます。
十五夜が終わっても、もう一度お月見を楽しめる機会があるというわけです。
また、十日夜は11月下旬に行われることが多いため、
「お月見は11月にもある?」という疑問につながるのです。
お月見には何をする?食べ物や飾り・ススキの意味も紹介
お月見では、月を眺めるだけでなく感謝の気持ちを表す行事でもあります。
十五夜や十三夜では、「お月見団子」や「里芋」「栗」「枝豆」など、
季節の収穫物を供えて月を愛でる風習があります。
十三夜は「栗名月」「豆名月」とも呼ばれ、
栗や豆をお供えすることが多いです。
飾りとしては、「ススキ(芒)」を立てるのが定番です。
ススキは、稲穂の代わりに神様を迎える目印とされ、
魔除けの意味もあると伝えられています。
また、最近では子どもと一緒にお団子を作ったり、
月をテーマにした工作や絵本の読み聞かせなど、
家庭でも気軽に楽しめる「月見の過ごし方」も人気です。
お月見団子やススキ飾りなど、お月見の準備にぴったりな商品を楽天で探せます。
手軽に揃えられるセットや、季節限定の和菓子も人気です。
お月見はいつ?11月の月見行事まとめ
お月見といえば9月や10月のイメージが強いですが、
11月にも伝統的な月見行事があることを知っておくと季節の深まりをより楽しめます。
- 2025年の十三夜は11月2日(日)
- 十日夜は11月29日(土)
十三夜は十五夜と並ぶ日本の伝統的なお月見文化のひとつ。
十日夜は、月をきっかけに収穫や自然に感謝する祭りです。
秋が深まる11月。
夜空を見上げながら、日本の風習や季節の美しさに触れてみてはいかがでしょうか。
秋の夜長に、団子やススキ、和菓子を準備して、
本格的なお月見のひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。