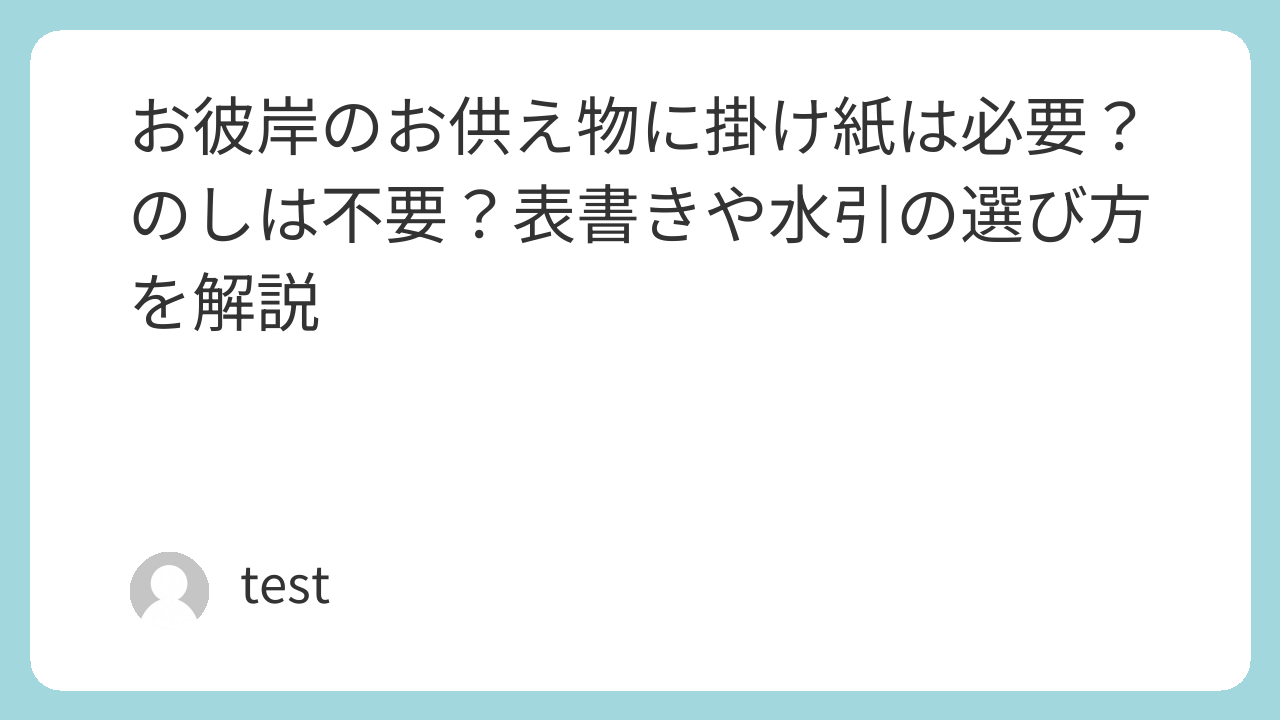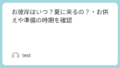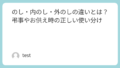結論から言うと、お彼岸のお供え物には掛け紙は必要ですが、「のし飾り」は付けないのがマナーです。
のしは慶事用の飾りであり、
お彼岸のような弔事には不適切とされているため注意が必要です。
この記事では、
- 掛け紙とのし紙の違い
- お彼岸にふさわしい表書きの書き方
- 掛け紙の種類と水引の色の選び方
- 外のし・内のしの使い分けまで
仏事の基本マナーをわかりやすく解説しています。
お彼岸のお供え物に掛け紙について|のしは不要?仏事の基本マナーとは
※2025年のお彼岸「お布施」の金額・封筒の書き方はこちらでまとめています
https://sarunanred.com/ohiganohusekingaku/
お彼岸のお供え物には、掛け紙をかけるのが一般的なマナーです。
贈る相手が家族や親戚であっても、
正式な場にふさわしい形で気持ちを伝えるために、掛け紙は付けた方が丁寧とされています。
ただし、ここで注意したいのが「のし」の扱いです。
のし(熨斗)は本来、慶事=お祝い事専用の飾りです。
そのため、お彼岸や法事などの仏事では、のしは付けてはいけません。
掛け紙とのし紙はどう違う?
掛け紙とは、贈り物の包装紙の上にかける紙のことで、
水引だけが印刷されたものや、無地のものも含まれます。
のし紙とは、その掛け紙の一種で、のし(熨斗)と水引の両方が印刷されたものです。
のしは元々「のしあわび」という縁起物を表しており、
結婚や出産、長寿祝いなど、お祝い専用の意味を持ちます。
したがって、お彼岸では「のしなし」の掛け紙を使うのが正しいマナーです。
のし・内のし・外のしの違いとは?弔事やお供え時の正しい使い分け>>>
「御供」と「御仏前」どっちが正しい?お彼岸の表書きの書き方ガイド
掛け紙の中央に書く「表書き」も、お彼岸では重要な要素のひとつです。
仏事の表書きには複数の種類がありますが、
お彼岸のお供え物には「御供(おそなえ)」が最も一般的です。
よく使われる表書き
- 御供(おそなえ):時期・宗派を問わず使える万能タイプ
- 御仏前(ごぶつぜん):主に四十九日以降に使われる表書き
- 志(こころざし):お返しや香典返しに使われることが多い
迷ったときは、「御供」を使えば失礼になることはほとんどありません。
水引の下には、自分の名前や家族名、会社名などを縦書きでフルネーム記入するのが基本です。
連名の場合は代表者を中央に書き、他の名前はその左側に並べます。
お彼岸に使う掛け紙と水引の種類|地域差や包装の仕方もチェック
掛け紙には、水引の色や本数の違いがあり、地域によって習慣が異なる点に注意が必要です。
水引の色の違い(仏事用)
| 種類 | 使用される地域・特徴 |
|---|---|
| 黒白 | 全国的に使用される一般的な弔事用 |
| 双銀 | 関西・中部地方でよく使われる |
| 黄白 | 東海・北陸地方に多い仏事用 |
お彼岸では、上記のような落ち着いた色の水引が印刷された掛け紙を選びましょう。
掛け紙のかけ方:外のし?内のし?
基本的には、**包装紙の上からかける「外のし」**が仏事には適しています。
※ここで言う「のし」は、「掛け紙の位置」を表す用語であり、飾りとしての「のし」とは異なります。
ただし、配送や簡易包装の場合は「内のし(包装紙の内側に掛け紙)」でも問題ありません。
包装と掛け紙の使い分けに迷ったら
店舗で注文する際は「仏事用の掛け紙で、のしは不要です」と伝えると安心です。
最近では、ネット注文時にも「のしを付ける/付けない」や「仏事用掛け紙」の選択肢が設けられていることが多くなっています。
お彼岸のお供えマナーまとめ|掛け紙・のし・表書きの正しい選び方
お彼岸のお供え物に関するマナーは、形式にとらわれすぎず、相手を思いやる気持ちを第一に考えることが大切です。
最後にもう一度おさらい
- 掛け紙は必要? → はい、基本的には丁寧さの意味で必要です。
- のしは必要? → いいえ、仏事では不要です(のしなし掛け紙を選ぶ)
- 表書きは? → 「御供」が基本。場合によっては「御仏前」も。
- 水引は? → 黒白・双銀・黄白など地域ごとの慣習に合わせて選ぶ。
- かけ方は? → 外のしが基本。配送時は内のしでもOK。
形式を守りつつ、故人を偲ぶ気持ちと相手への心配りが伝わる形にすること。
それが、お彼岸のお供えにおける一番のマナーです。