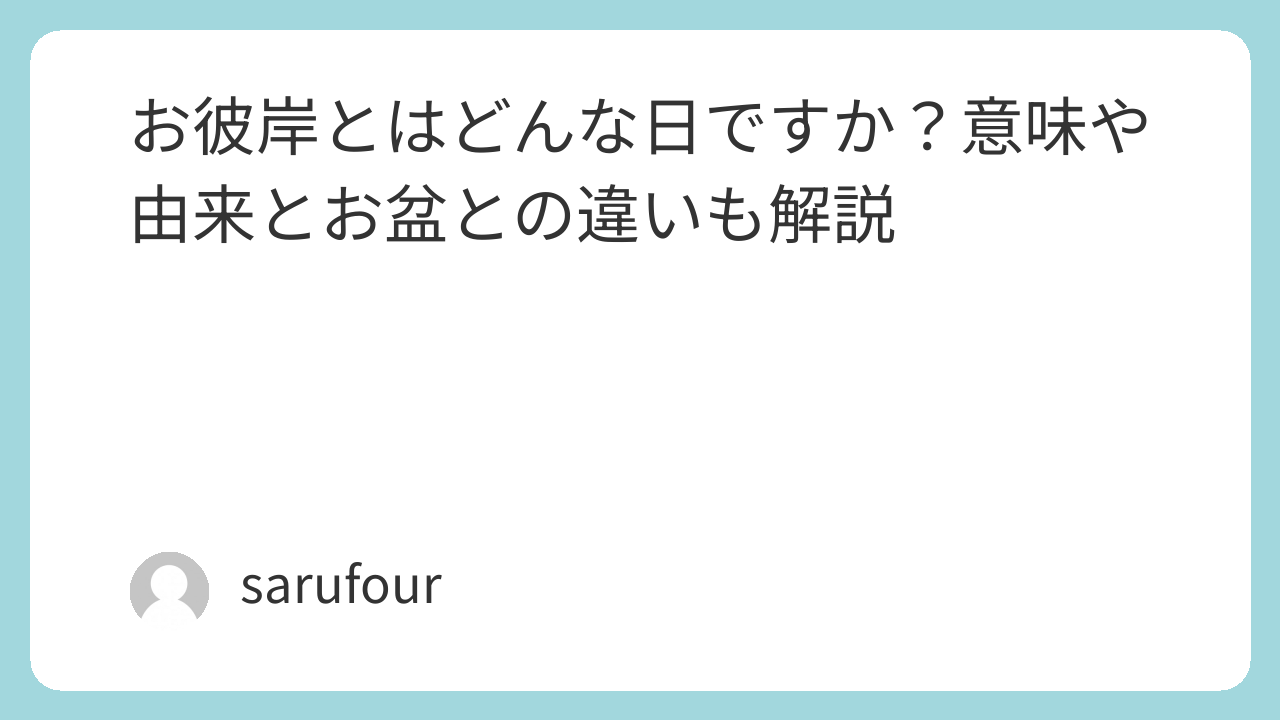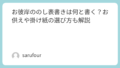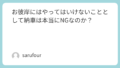結論:お彼岸は、仏教に基づく“感謝と供養の日”で、春と秋に7日間ずつ行われます。
実はお彼岸は、春分・秋分の日を中心に行う日本独自の仏教行事で、ご先祖様への供養や感謝を表す大切な期間です。
この記事では「お彼岸とは何か?」「いつから始まるのか?」「お盆との違いは?」など、意味・時期・習慣・注意点を詳しく解説します。
お彼岸とはどんな日?意味や由来をわかりやすく解説
※2025年のお彼岸のお布施金額や封筒の書き方はこちらでまとめています
https://sarunanred.com/ohiganohusekingaku/
お彼岸とは、仏教の考えに基づく供養の行事で、春分と秋分の前後3日間を含む7日間に行われます。
「此岸(しがん)」=現世と「彼岸(ひがん)」=悟りの世界がもっとも近づく特別な期間とされ、心身を整えてご先祖様に感謝を捧げる時間です。
仏教で使われる「到彼岸(とうひがん)」という言葉は、煩悩を超えて悟りに至るという意味があります。
その教えにならい、お墓参りや仏壇へのお供えを通して、先祖を敬う心を表します。
「お彼岸って何をする日?」と疑問に思っていた方も、まずは感謝と供養の日だと覚えておくとわかりやすいでしょう。
お彼岸の期間はいつからいつまで?中日や春・秋の違いも紹介
お彼岸は毎年春分と秋分の日を中心に前後3日ずつ、合計7日間あります。
たとえば、2025年の春のお彼岸は3月17日〜23日、秋のお彼岸は9月19日〜25日です。
春分・秋分の日は太陽が真東から昇り真西に沈むため、「あの世とこの世がつながりやすい」とされ、**中日(ちゅうにち)**は特に大切な日と考えられています。
春のお彼岸には「ぼたもち」、秋のお彼岸には「おはぎ」をお供えするなど、季節の食文化も根づいています。
なお、お彼岸は仏教行事のなかでも日本独自の習慣であり、他国の仏教圏ではほとんど見られません。
お彼岸とお盆の違いは?共通点と仏教行事としての位置づけ
お彼岸とお盆はどちらも先祖供養の行事ですが、その目的と由来には違いがあります。
お盆は「ご先祖様の霊が帰ってくる期間」であり、迎え火・送り火などを通して一時的に現世に招く行事です。
一方、お彼岸はあの世に思いを馳せる期間で、こちらから供養を届けるという意味合いが強いです。
また、お盆は旧暦の影響から地域によって時期が異なるのに対し、お彼岸は全国共通の日程で実施されるのも特徴です。
どちらも仏教行事ですが、お彼岸のほうがより静かで内省的な印象を持たれることが多いでしょう。
お彼岸にやること一覧!墓参り・お供え・やってはいけないこととは
お彼岸にすることの代表は、墓参りと仏壇へのお供えです。
お墓を掃除してお花や線香を手向け、手を合わせて感謝の気持ちを伝えます。
また、仏壇には季節の食べ物や故人が好きだったものをお供えし、家族で一緒に過ごす時間を大切にします。
食べ物の例としては、「おはぎ(秋)」「ぼたもち(春)」、そして果物や和菓子などが人気です。

お彼岸のお供えとして定番の「おはぎ」も、通販で購入できます。
一方、「やってはいけないこと」として特別な禁忌はありませんが、殺生(生き物を殺す行為)を避ける、騒がしくしないなど、静かに心を整えることが大切とされます。
旅行や外出の予定がある場合でも、できれば中日を中心に供養を行うのが望ましいとされています。
お彼岸とはどんな日なのか?【まとめ】
お彼岸は、春と秋の年2回行われる仏教の供養行事です。
ご先祖様に感謝し、墓参りや仏壇のお供えを通じて心を整える期間です。
春分・秋分の日を中心に7日間あり、中日は特に重要な日とされています。
お盆との違いも理解しつつ、家族で先祖と向き合う時間を大切に過ごすことが、お彼岸の本来の意味です。
忙しい現代だからこそ、静かに自分と向き合うお彼岸の習慣を続けていきたいですね。